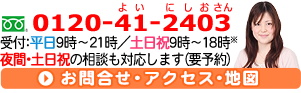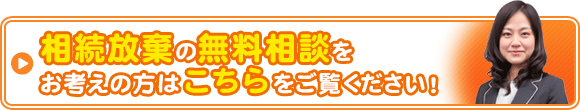相続放棄の条件
1 相続放棄の条件
家庭裁判所に対して相続放棄の申立てを行う場合、相続放棄の要件に該当しているか否かという点を厳しくチェックされることになります。
そのため、今回は、相続放棄を行うことができる条件について解説していきたいと思います。
民法上の相続放棄の要件としては、以下のようになります。
①相続の開始があったことを知った日から3か月が経過していないこと
②相続の単純承認及び限定承認をしていないこと
③法定単純承認事由に該当しないこと
2 ①相続の開始があったことを知った日から3か月が経過していないこと
相続放棄は原則として、自身のために相続の開始があったことを知った日から3か月が経過した場合には、行う事が出来なくなってしまいます。
「相続の開始があったことを知った日」とは、被相続人の死亡等の相続開始の原因たる事実を知っただけでは足りず、それによって自身が相続人になったことを明確に認識した時とされています(大判大正15年8月3日、仙台高決昭和59年11月9日)。
そのため、自分よりも先順位の相続人がいると誤信していた場合等には、誤信が解消した時が「相続の開始があったことを知った日」に該当する可能性があります。
3 ②相続の単純承認及び限定承認をしていないこと
相続には、相続放棄以外に単純承認及び限定承認という2つの選択肢があります。
それぞれを簡単に説明すると、「単純承認」は、相続をする意思表示のことを指し、「限定承認」は相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する制度を指しています。
相続放棄を行う前に、これらの単純承認や限定承認を行っていた場合には、相続放棄とは相反する行為のため、相続放棄はできなくなってしまいます。
4 ③法定単純承認事由に該当しないこと
上述の単純承認は、基本的には意思表示であることをご説明しましたが、単純に相続したということを第三者に伝える事だけではなく、法律上単純承認に該当する行為が明確に定められています。
このように、法律上、単純承認を行ったものと擬制されてしまう行為のことを法定単純承認事由(民法921条各号)と呼びます。
参考リンク:民法 e-Gov法令検索
民法に法定されている事由をまとめると、以下のようになります。
ア 相続財産の処分を行った場合
イ 相続の開始を知った日から3か月以内に限定承認又は相続放棄を行わなかった場合
ウ 相続人が限定承認や相続放棄を行った後であっても相続財産の一部を隠したり、消費したりした場合
ア 相続財産の処分を行った場合
「処分」とは、相続財産を売却することや、費消すること等、所有者でなければ通常行うことができないと考えられる行為をいいます。
例えば、遺産の車を売却したり、遺産のお金を使いこんでしまった場合がこれに該当します。
少し判断が難しいものとして、葬儀費用の支出を遺産から行った場合や、故人の服を形見分けした場合などがあります。
判断に迷うことがあれば、弁護士に相談されることをおすすめします。
イ 相続の開始を知った日から3か月以内に限定承認又は相続放棄を行わなかった場合
上述のとおり、相続の開始を知った日から3か月以内に限定承認も相続放棄も行わなかった場合には、もはや相続をうけいれたものとして扱われるため、単純承認事由に該当すると考えられます。
ウ 相続人が限定承認や相続放棄を行った後であっても相続財産の一部を隠したり、消費したりした場合
全ての相続人が相続放棄を行った場合、故人の債権者は、残った遺産を分配して、債権の弁済に充てる事になります。
そのため、相続人は自身が現に占有している遺産について、自分の所有物に対する注意と同一の注意義務のもとで保管する必要があるとされています(民法940条1項)。
この義務に反して、相続放棄後に遺産を他の相続人や債権者から隠したときには、単純承認事由に該当するものとして、相続放棄の効力が否定されることになります。
そのため、故人と同居していた場合等に相続放棄をする場合には、他の相続放棄を行った者よりも相続放棄後の責任が重くなる可能性があるといえます。
以上のように、相続放棄を行う条件には厳格なルールが定められていますので、適切に相続放棄を行うためにも、まずは弁護士にご相談ください。
遺産分割協議はやり直せる?やり直しの期限・税金との関係も解説 家族信託を依頼する専門家